| Hallow Eve ただ、呆然とした。 頭の中では、エクスクラメーションマーク=!とクエスチョンマーク=?が跋扈している。 「なっ、なんだこれはーーっ!!」 「何って、カボチャだよ」 返事が帰ってくるとは思わなかった。 玄関を振り向くと、黒いスーツを肩にかけネクタイを弛める男。 「見れば分かるわっ!!俺が言いたいのは、」 「どうして、こんなにいっぱい此処にあるのかって?」 「そうだっ」 ついつい荒くなってしまう息を抑えて睨みつければ、やつは困ったような笑みで見返してきた。 それに思わず眉を寄せると、さらに楸瑛の苦笑は深くなる。 「私に言われてもね、…………どうしてなんですか?」 そう言うとやつは、俺の後方に視線を投げた。 その問い掛けに、失念していたもう一つの可能性に思い当たる。 そうだった、こんな馬鹿なことを喜々として計画しそうなやつが、もう一人いた。 そしてこういう時の感とはえてして当たるもので。 「ふっふっふ、決まっているのだっ!!楸瑛、絳攸!」 今日はハロウィンなのだっ!! 胸を張って発せられた単語に、頭が痛くなる。 何故俺の周りには、こうもアホらしく季節の行事に傾倒する人間が多いのか。 「んな事、知っているわっ。だから、それが何で此処まで酷い有様になるっ!?」 見渡す限り、カボチャカボチャカボチャ。キャンドルキャンドルキャンドル。 そして、その中心。中が刳り抜かれた一際巨大なカボチャが鎮座するテーブルの上には、 2段重ねのこれまた異様に大きなホールケーキ。 決して小さくはない4,5人用のテーブルが、今は子どもの玩具のまる机に見えるのは何故だろう。 理解したくはない、そう思った。 「もしかしないでも、あれ。食べるんですか?」 俺の横に並んだ楸瑛が、恐る恐るといった感じで尋ねる。その顔は、心なしか引きつっていた。 まぁ、そうだろう。甘い物好きの俺ですら遠慮したくなるほどの量を、 どちらかと言えば苦手な部類に入る楸瑛に完食しろとは。 「当然だっ、せっかく一生懸命作ったのだ、食べなければもったいないぞっ!」 「……貴様っ、何処にそんな時間が」 「うっ、が、頑張って夜遅くまで起きて用意した」 「なるほど。それで此処最近眠そうだったんですね」 楸瑛の得心がいったという風情の声に、頭を抱える。 突っ込む場所が違うだろう、常春。 否、確かに通常通り仕事をしながら何時こんなにも大がかりなことをする時間があったのか、 大いに気になることではあるけれど。 というより、そのために早く帰りたいだのとぬかしてやがったのか。 (今度から、もう少し容赦なく仕事を押しつけてやろう) って、そうでもなくてだな。 問題は其処じゃない。 「分かりました。あなたが仕事中も此方の方にばかり気が入って、 微妙に業務が捗らなかったことも、俺の前で欠伸をされて腹が立ったことにも、この際目を瞑ります」 「うっ、こ、絳攸」 俺の数段低くなった声に目の前の青年が怯もうがどうなろうが関係ない。 にっこりと、普段はけして見せない表情を向けてやる。 その瞬間、彼の口からヒッと悲鳴の出来損ないらしきものが漏れたが、そんな事知ったことか。 自業自得だ、と切り捨てた。 「そして、上司のあなたがハロウィンを楽しもうが勤務外の時間に何をして過ごそうが、 全く私達の関与する所じゃないので、何も言いませんよ。ただ、」 そこで一拍置く。深く息を吐いて、そして吸い込んだ。 「何故、よりにもよって俺の部屋でするっ!? というか、どうやって入った!この不法侵入者がっ、訴えるぞっ!!」 「ご、ごめんなさいっー、」 涙をうるうると溜めながら謝り倒してくるのにも、今は同情の余地もない。 「許さんっ!せっかく掃除したのに、逆戻りだろうがっ」 「絳攸、それはちょっと酷くないかい?」 「何がだ、常春頭。毎度毎度被害を被る俺の身にもなってみろ!」 「そうだけど、……」 そう言うと、ちらっとリビングの角で膝を抱えている暗い物体の方へと視線を動かした。 こいつの言いたいことは分かる。 だがそれとこれとは話が全く別だ。 目だけで睨め付けるように訴えると、やれやれと言った風に肩を竦められた。 何なんだ、その態度は。 (まるで、俺が悪いようじゃないか、) あり得ない。 確かに少し、言い過ぎたし仮にも夕食を用意してくれて、簡素な部屋を飾り付けてもくれたし。 実際、こんな事がなければ、楸瑛とちょっとぐらい、 ほんの申し訳程度のジャック…オ…ランタンをテーブルの端にでも置いて楽しむつもりだったし。 だから、夜鍋して作ったというこのカボチャケーキ(何故こんなにも精巧に作れたのか、不思議でならない) を、遠回しにでもごみ呼ばわりした事は、少し、悪かったと思う。 (だが、) 普通の常識を持つ人間が、仕事尽くめで疲れて家に帰ってきて この光景を見せられれば、理性の糸の一つや二つ切れても文句は言われない、だろう。 (駄目だ、自身が無くなってきた) 「絳攸、」 呼ばれて顔を上げれば、穏やかに先を促す楸瑛がいて。 もう一度その先に目を向ければ、さっきまで『の』の字を書いていた上司は、 暗い雰囲気を纏いながら此方を向いていて。 「っわ、分かりました!祝えば良いんでしょうがっ、」 ひたすら見つめてくる4つの瞳に耐えきれなくなって叫べば、 あからさまに目を輝かせてはしゃぐ彼に余計に気恥ずかしさが募る。 「こらっ、暴れるな。下の人に迷惑が、って常春!何笑ってるっ!」 「いや、…………別に、何でも……ないよ」 堪えることの出来ない笑いに声を震わせていて、何が何でもない、だ。 顔が熱い、冷まし方も分からない。くそっ、だから嫌いなんだ。 「さっさと始めるぞっ!とにかく、これを片づけないと料理もできん!」 「おやっ、今日は君が作ってくれる気だったの?嬉しいな、久々の君の手料理だ」 「貴様はぁ〜〜っ、」 言い合いながらも、キャンドルカボチャやらお化けぬいぐるみやらを掻き分けて 椅子に座ろうとすると、突然制止がかかった。 「ま、待つのだ!二人とも!何か大事なことを忘れているのだっ」 「なんだ、まだ何かあるのか?また厄介な事じゃないだろうな」 「なんです?」 俺に続いて楸瑛も首を傾げて、劉輝を見る。 すると、待ってましたと言わんばかりに解けてしまいそうなほど顔を弛めて。 「トリック・オア・トリート!!」 と、のたまった。 3人の男の間をヒュルッと木枯らしが吹き去った。 やはり秋も深まってきた、と肌で感じた瞬間、横の男が堪えきれずに噴出した。 「アハハ、なるほど。……確かに、忘れてましたね」 個人的には、朝一で絳攸に言って見事飴をもらったんですが。 「フフ、……もう一度、今度は悪戯をするのも悪くないかな」 笑いを噛み殺しながら、ねぇ絳攸、と意味ありげな視線を投げかけてくる。 飴、と言った時点でこいつの言いたいことなど解りまくっていたので、 容赦なく足を踏みつけたのに、悔しいことに全く効いていない。 (お前の頭にはそれしかないのかっ、) 「うぅ〜、楸瑛に先を越されてしまったか」 今朝の事を仄めかされて否応なしに高まる緊張を知ってか知らずか、 天然上司はのほほんと少し残念そうに呟く。 「うん、仕方ないのだ。気を取り直して、トリック・オア・トリートだ」 しかも何自己完結してるんだ、話が全く繋がっていない。 だが、常春はそれを気にする様子もなく「Trick or Treat、ですよ」と発音指導をしている。 本当に、どうしてこいつらといるとこうも疲れるのだろう。 考えても埒があかない問いに見切りを付けて、ポケットに入っていた丸い物を取り出す。 避けられることを承知で、力一杯劉輝に投げた。 それを慌てて受け取る姿から目を逸らして。 「それしか持ってないが、此処にケーキがあるんだ。文句はないだろっ」 早口で捲し立ててドカッと自分の席に腰を下ろした。 「クスクス五月蝿いっ、この万年常春頭馬鹿男っ!!」 八つ当たりに怒鳴ると、ますます笑みを深めるこいつが本気で憎らしい。 「はいはい、それじゃあ電気を消しますから。ちゃんと席について下さい」 「分かったぞぉ〜!」 顔全面に喜色を浮かべてふにゃふにゃと口を動かす青年を向かいに座らせて。 そして、間もなく世界は暗転した。 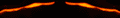
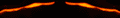 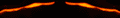 フリー配布期間終了。 date:2006/10/15 By 蔡岐 |
