|
路傍に落つる紅葉 「うん?そういえば、楸瑛はどうしたのだ?」 「何で俺に聞くんですか、・・・・・・知ってる訳、ないでしょう。」 劉輝はうっと怯んだ後、少し眉を寄せた。 そして、何か思いついたように顔を明るくした。 それを見て今度は絳攸の眉間に皺が寄った。 「うむ!そうなのだっ!」 何が、と絳攸は心中で突っ込んだ。 それに気づいているのか、いないのか。 劉輝は一人でうんうんと頷きながら書類だらけの机から抜け出した。 「おい、」 「ん?どうしたのだ、絳攸。」 「それはこっちの台詞だっ!仕事放り出して、何処へ行くつもりだ!!」 怒鳴ると彼は心底驚いたような顔で目を見開いて、 「・・・・楸瑛の所なのだ。絳攸は、行かないのか?」 絳攸は自分の予想が当たったことを知り、額に手を当てた。 「それでわざわざ此処まで来たわけですか、・・・・」 にこにこと笑顔を振りまいている王に声をかけながら、 楸瑛はその隣で刺すような視線を向けてくる同僚からそっと目を逸らした。 機嫌が悪い、かなり悪い。 (恨みますよ、主上) 絳攸の不機嫌の原因は、相変わらず邪気のない笑顔を向けてくる。 これが故意のものであったら相当の鬼畜だが。 残念というか、全くの純粋な心なのだから、あからさまに非難するわけにもいかない。 「それでだ、楸瑛!余は楸瑛の、羽軍での様子が見たいぞっ!」 ((何が、『それで』、だ)) 二人同時に突っ込んだ。もちろん心の中だけで。 あるいは、此処が執務室なら、怒鳴り散らして頭を叩くことも出来ただろうが、 左羽林軍の、しかも多かれ少なかれ何も知らない武官のいる前で、 仮にも『主上』を害することは、さすがの絳攸でも出来なかった。 と、その時。 一人の年若い武官が近づいてきた。 「あの、・・・お話中申し訳ありません。藍将軍、」 「ん?ああ、韓升。どうしたんだ?」 「はい、実は黒――――」 「おお!そなたは、楸瑛の部下か!?」 突然言葉を遮られ声をかけられて、瞠目し狼狽えている韓升に、楸瑛が助け船を出す。 「構わないよ、話してくれ。主上、彼の事は後で紹介しますから。」 「あっ。・・・うむ、すまなかった、先を。」 続けてくれ、と言われ、韓升は恐縮しながらも話し出した。 キィ――ン キィン 絶え間なく響く剣と剣のぶつかる音、 そしてそれ以上に高まっていく周囲の緊張感。 文官の自分ではまず体験することのない、一種異様な雰囲気に飲み込まれそうになるのを堪えながら、 絳攸はなんとか目の前の試合に意識を集中しないようにした。 隣にいる青年は、さきほどから既に一言も発さずに鍛錬場の中で繰り広げられる演舞に見入っている。 (そういえば、こいつは宋太傳に武術を習ったんだったか、) 前に楸瑛が言っていたのを思い出す。 だからだろうか、剣というものにさほど恐れを抱いていないのは。 それともそれが普通で、おかしいのはまともに柄を握ったこともない自分なのか。 ちらり、と周囲を見渡せば官吏よりも遥かに均整の取れた体つきの男達。 左羽林軍に所属する精鋭の武官の姿ばかり。 自分のような文官はどこにもいない。 (当たり前、か) 日が傾きかけているとはいえ、こんな時間にこんな場所を文官がうろうろしているわけがない。 「李侍郎、」 突然かけられた言葉に、驚いて後ろを振り返ると、そこには先ほど楸瑛に話しかけた武官がいた。 (韓升、といったか) 彼は黒大将軍からの連絡を伝えに来たのだ。 つまりは、― 相手をしろ ― という命令を。 韓升や他数人の武官によれば、 主上付きになり、側近となった楸瑛は、羽軍の詰め所にいることが格段に少なくなった。 自らの上司が‘花’を賜った事を誇る一方で、有能な武人の不在を嘆くものも少なくないのだという。 だから、たまに此方の方に詰める時は、通常の何倍もの稽古をつける、らしい。 「ご気分がお悪いのですか、」 考えている間に、どうやら人混みからは脱出したらしい。 彼が気を遣って連れだしてくれたのだ、 試合に見入る者達の中で、一人俯いて眉間に皺を寄せる俺がよほどおかしく映ったのだろう。 「いや、大丈夫だ。・・・・・すまなかった。」 彼だって本当は楸瑛と黒大将軍との手合わせをしっかりと見ていたかったはずだから。 あれほど白熱した試合は、そうそうあるものではないだろうに。 「その様な、・・・構いません。 むしろ、見て見ぬ振りをした方が、後々恐ろしいことになりますよ。」 笑いを含んで言われた言葉を図りかねていると、 韓升は急に表情を引き締め、少し緊張した不安げな瞳で静かに尋ねてきた。 「その、李侍郎は。・・・・・武官がお嫌いですか?」 「は?・・・・何故そんな事を。」 「いえ、その。・・・・・李侍郎が、険しい表情で試合をご覧になっておられたので。」 言いにくそうに、しどろもどろに話す韓升の目は絳攸には合わされない。 その態度に、1つの可能性が浮かんだ。 「本当にそうか?ちゃんと言ってみてくれ。」 静かに、努めて穏やかな口調で問い掛けると、相手は驚いたように視線を向けてきた。 (やはり、) 俺が不快に感じると思ったのだろう、合わされた目には困惑が見て取れる。 それをしっかりと見返すと、やがて韓升は目を伏せ言葉を探すように視線を巡らせた後、ゆっくりと再び顔を上げた。 「李侍郎が、・・・血を。 ―――― 将軍の傷を見て心を痛めておられるようだったので。」 瞬間、静かに目を閉じた。 (ああ、よく見ているな。) 楸瑛が目をつけるだけのことはある。 その観察眼、情報分析は対したものだ。 見透かされていたことに、自然と腹は立たなかった。 date:2006/11/18
「別に、・・・・いいや、疎んでいる訳じゃない。」 それは本心だった。 真実では、なかったけれど。 韓升もそれが分かっているだろうに、何も言ってこない。 ただ、俺が続きを紡ぐのを待っている。 「嫌っていない、ただ、・・・・・」 そこでふいに言葉が途切れた。 そう、嫌いな訳じゃない。 悔しいだけだ、 ただ、それだけ。 「そうだな、歯痒いのかも知れない。」 「歯痒い、ですか。」 怪訝に眉を寄せるのを見て、苦く笑った。 おかしな事を言っているのかも知れない。けれど楸瑛を知り、 彼を慕う部下に、どうしても話してしまいたかった。 「俺は剣の振り方を知らない、握り方すら。」 上司の試合を一目見ようと、群がっている方を見ながら話す。 僅かに身動いだ気配がした。 おそらく目を見開いているのだろう。 「武人が剣を振るう時は、 国や己や誰かを守るために他者を殺す時だと、藍楸瑛は言っていた。」 「はい、だから私達は日々の鍛錬を欠かしません。」 瞬時に返された言葉に小さく笑みがこぼれた。 (まったく、あいつと同じ事を言う) 羽軍のやつらはみんなこうなんだろうか、変な覚悟ばかり決めていて。 「俺は、戦場に出ることは出来ない、・・・それが悔しいのだと思う。」 「李、侍郎・・・・・」 韓升は懸命にもそれから先を言わなかった。 突き刺さるような視線は、彼の驚きと懸念が嫌と言うほど含まれていたけれど。 「大丈夫だ、それほど愚かなことはしない。そう言う意味じゃないんだ。」 「では、どのような」 当然の問いに、僅かに目を瞑った。 「俺は戦場には行けない。足手まといとか、そう言うことではなくて。 耐えられないだろう、剣が人の肉を貫くことに。それを行う者にも。きっと、耐えられない。」 韓升は黙って聞いていた。 その様子に小さく笑いかけた。 「殺らなければ殺られる、戦では。戦場に出れば、・・・俺は、仲間を殺してしまう。」 ワァ ――――― ッ 歓声が響く。 慌てて其方を向くと、ちょうど黒大将軍が楸瑛に突きつけていた剣の切っ先をさげるところだった。 その瞬間、全身の血が沸き立ち、汗が噴き出た。 「李侍郎、」 韓升が気遣わしげな視線を向けてくる。 それにどうにか返事をし、向こうに言って構わないと目で促した。 韓升は何か言い足そうにしながらも僅かに頷いて、仲間の元に小走りで向かっていった。 けれど、 「それでも、伝えるべきだとおもいますっ!」 聞こえた声にはっと前を見ると、ちょうど彼の背中が完全に輪の中に消えたところだった。 date:2006/11/23
「絳攸!何処へ行っていたのだっ!」 ゆっくりとした足取りで詰め所に戻ると、腰に手を当てて珍しく不機嫌顔の主上がいた。 ぶくっと子どものように頬を膨らませた彼が、今は何故か凄く可愛く感じる。 知らず微笑んでいたのか、劉輝が今度は目を見開いて固まってしまった。 楸瑛はまだ、帰ってきていない。 あいつより一足は早く、残りの書簡を処理するべく執務室に戻ったのはいいが、まったく執務に身が入らない。 やはり、あんな話などするべきではなかったのか。 真面目そうな彼にも、迷惑をかけてしまった。 (もし、あいつが出兵したら、俺は、) 考えるだけ無駄なことは、嫌と言うほど解っている。 楸瑛といると、本当に無駄な考え事が多くなる気がする。 その時、扉が開いた。 「おおっ!楸瑛、凄かったな。」 顔が見えた途端に、目を輝かせて立ち上がった劉輝に、楸瑛が苦笑して座らせた。 「ありがとうございます、主上。煽てても、何も出ませんけどね。」 「うっ、別に手伝って欲しくて言ったわけではないのだ。」 口を尖らせて言っても説得力はない。 突っ込む気にもならず、二人のやりとりを見ていると何故か同時に此方を見てきた。 「・・・なんだ?」 「えっ?いや、・・・・・」 「絳攸、どうしたんだい?」 何故楸瑛に尋ねられたのかも分からない。 眉を寄せて黙り込むと、はぁーと溜息を零された。 「なんだっ、」 「まったく君は。」 大仰に手を広げて嘆いている。 それが、どうしようもなく腹が立つ。 「だから何なんだっ!」 怒鳴った俺を綺麗に無視して、楸瑛は主上に何か小声で囁いた後、此方へ大股で歩いてきた。 「な、何だ、」 「絳攸、ちょっといいかな。」 もっぱら確認のようにそう言うと、有無を言わせず腕を掴まれ、そのまま引きづられるようにして執務室を出た。 「おいっ!楸瑛!」 怒鳴って掴まれた腕を引きはがそうとするが、さすがは将軍と言うべきか、びくともしない。 そうしている間にも、楸瑛は俺を連れてどんどん人気のない方へ移動している。 日が暮れて時間が経ているからか、すれ違う者も少ない。 「楸瑛っ、聞いてるのかっ!?」 「聞いているよ、」 やっと返事が返ってきたと思えば、急に歩みを止められて思いっきり奴の背中にぶつかってしまった。 楸瑛がかすかに笑った。羞恥心で顔が真っ赤になる。 「絳攸、ちゃんと前を見て歩こうね。」 「うっ、五月蝿い!!貴様が無理矢理引っ張ってきたんだろうがっ!」 間違ってはいない、まぁ少し言い訳くさいが。 「それはすまなかったね、」 楸瑛は悪びれることなく、振り返ってにこりと笑った。 そのなんの感情も含まれていない笑みに、うっと怯む。 別にやましいことをした覚えはないのだから、 (というよりむしろこいつの方がよほどしまくっているはずだ)どっしりと構えていれば良いはずなのに。 「・・・・・・絳攸、どうしたの。」 俺の肩に手を置いて、覗き込むように視線を合わせた楸瑛の目は、 先ほどの練習試合と同じくらい、酷く真剣だった。 それがあまりに強すぎて眩暈がする。 慌てて目を逸らした。 「絳攸、」 笑いの欠片もなく呼ばれた名は、碇のようで、振り解くことを許さない響きがあった。 「・・・・韓升に、・・何か言われた?」 「な、ちっ違う、」 違う、彼はなんの関係もない。 そう伝えたいのにどうしてかうまく言葉に出来ない。 これでは、心優しいこいつの部下にあらぬ疑いをかけることになる。 「楸瑛、ち、がうんだ。お前の部下が悪い訳じゃ、なくて、ただ・・・・」 「ただ、?」 問い返してきた楸瑛にさきほどまでの激しさはなく、その事に安堵した。 柔らかな口調でゆっくりと続きを促してくる。 (言っても、いいものだろうか。) 韓升はああ言っていたが、それはあくまで暗い思考に走っていた俺を浮上させるための方便ではないのか。 だいたい、武官に向かって「誰も傷つけるな。」なんて。 何よりも言ってはならない事、ではないのか。 「絳攸、」 呼びかけに恐る恐る視線を上げると、仄暗い視界の中で、楸瑛の輪郭が僅かにぼやけていた。 温かなものが俺の乾いた唇に被さる、すぐに離れていってしまったけれど。 気が付けば身体ごと楸瑛の中にいて。 「絳攸」 あやすように名を呼ばれ、背中を優しく叩かれた。 いつもなら即罵声を飛ばすはずの行為が、今は酷く恋しくて嬉しくて。 「・・・・絳攸?」 藍の衣にこぼれ落ちる滴は視界に入れないように、目を瞑った。 聞こえてくるのは、俺と楸瑛の心音だけ。 「お前は、・・・・・ここに、いるんだな。」 「え?・・・ああ、いるよ。君の目の前に。」 驚きながら、それでも言葉を返してくれる。 (やはり、左羽林軍に在籍しているだけはあるな、) 彼には、韓升には最初から分かっていたのかも知れない。 例えどんなことを言われても楸瑛は揺らいだりしない、と。 しっかりと受け止めて返してくれると、知っていて、背中を押したのかも知れない。 それは嬉しいけれど、・・・・少し、悔しかった。 「楸瑛、俺は、・・お前に剣を持って欲しくない。」 一定だった胸の振動が不自然に揺れた。 一瞬ではあったけど、背中に回された腕がぴくりと痙攣して、止まる。 「誰かを傷つけて欲しくない、誰にも傷つけられてほしく、ない。」 それは昼間の鍛錬で剣を握ったこいつを見て、最初に思ったこと。 武官姿のこの男が、真剣に黒大将軍と対峙していた時、ただただ願っていたこと。 「俺はっ、・・・・・誰かが傷つく姿なんて、見たく、ない!」 違う、本当は。 誰もが幸せで、なんて。できるわけがない。 そんな馬鹿げたことを望んでいるわけじゃなくて、『誰か』が傷つくのが嫌なんじゃなくて。 「うん、知ってるよ。・・・知ってるから。」 それでも、温かい楸瑛に治まりかけていたものが再び流れた。 (違うんだ。ただ、お前だけには、・・・・・) 全てを言わなくても、汲み取ってくれる。 俺はいつもこいつの好意に甘えてばかりで。 それでも、宥めて微笑ってくれるこの常春男は、どこまでお人好しなんだろうか。 「絳攸、」 掬い取られても、止めどなく流れる生温いものを、今度は舌で嘗め取って。 耳元での甘い囁きに、今だけは大人しく顔を向けておいた。 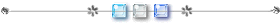 11月Blog掲載文 |