|
楸瑛+三つ子 , 〜 例えお前が疎んでも、 〜 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 「「「楸瑛」」」 部屋に入るなり聞こえてきた声に、思わずわずかに肩が震えた。 そのまま、回れ右をして退出しなかった自分に拍手を送りたい。 半ば予想していたこととはいえ、頭の中と現実とでは、やはり衝撃が違う。 目の前には、満面の笑みを浮かべた自分と類似する容貌が3つ。 そう、3つ。それが今回の、というよりも今までの人生の最大の問題かもしれない。 「・・・お久しぶりです、兄上。」 必死に頬が引きつらないように注意しながら、どうにかその言葉をひねり出した。 まだ何もしていないにもかかわらず、冷たい汗が背を流れてゆく。その感触がさらなる予感を煽った。 この鬼畜で自分や親族を弄ぶ事を趣味にしている人達に、口上であれ剣であれ、勝てると思ったことはない。 なにせ、あの、氷の長官と恐れられる紅黎深と対等に張り合える方々で。 しかも悪いことに、1人でも手に負えないのにそれが3人もいる。 ― 無理だ、絶対無理だ ― というか、そんな人間いたら余計に恐い。 彼らを(本人その気はないだろうが)意のままに動かせるのは、邵可様一人で。 それ以外はどうか御免被りたい。 どうせろくな事にならないのは目に見えている。 「どうした、楸瑛。」 目の前の一人、次兄がこれまた小首を傾げながら話しかけてきた。 「我らの顔に何か付いているか?」と実に楽しそうに、意地の悪い質問をしてくる。 ― 私がどうして黙っているかなど、とうに解っているくせに ― 入室時から、笑顔を絶やさない3人に冷や汗が頬を伝う。 機嫌が良い、すこぶる良い。気味が悪いほどの白い笑み。もちろん表面上だけだけれど。 兄達がご機嫌な時ほど、気を付けなければならない時はない。 今までも何度それで辛酸を嘗めてきたことか、思い出すだけで苦笑が漏れる。 今考えると。 あれは機嫌が良かったから無理難題をふっかけられたのではなく、 理不尽な要求に私が悩むのを想像して、それで上機嫌だったのだろう。何とも傍迷惑な話だけれども。 本当に、溜息が出そうだ。 いっそ出してやろうか、とも思ったがそんな事をした後の兄達の反応が恐すぎるので実行には移さない。 何事もうちに秘めるだけなら自由だ。不満も、己の願望も。 「楸瑛」 3人の中心にいる人物、長兄が口の端を歪ませて話し出した。 その表情は酷く楽しげで、見知らぬ人が見たら、おそらく酷く凶悪に感じただろう笑みを浮かべていて。 自分は藍本邸に帰ってきたのだと改めて認識した、感慨の欠片もないけれど。 「楸瑛、賭けをしよう。久々に帰ってきたんだ、 ちょっとぐらい、藍州から出られない哀れな兄達の相手をしろ。」 よく言う、いつも好きな時に好きな事しかしないのに。彼らが本気を出せば叶わないことはない。 つまりこの状況から逃れる術はない、兄達の気が済むまで付き合う以外は。 ― あぁ、帰りたい ― 紫州に、朝廷に。 常に迷子状態なのに決してそれを認めない彼は、どうしているだろう。 今この時も迷っているのだろうか、それとも吏部の机に齧り付いているのか。 喧嘩好きの上司二人はどうしているのか、 また変な意地を張ってとんでも無いことになっていなければいいが。 ほんの数日前のことなのに、何故かとても懐かしい。 兄達の奇行に辟易しているからか、それとも ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。 どちらにしても、この状況をどうにかしなければ私にまともな生活は帰ってきそうにない。 下腹にグッと力を入れ、兄達が用意した(何故か室のど真ん中にある)椅子に手を伸ばした。 例えお前が我らを疎んでも、それでも我らはお前を愛そう お前は、それだけのものを与えてくれた 別に気づかなくて良い、ただ傍らで苦笑してくれれば 〜End. 2006/09/27 By 蔡岐 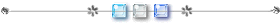 9月Blog掲載作品 読みにくかったので、句読点などをちょちょいと加筆修正。。。 最後の三行は唯書きたかっただけ・・・ |